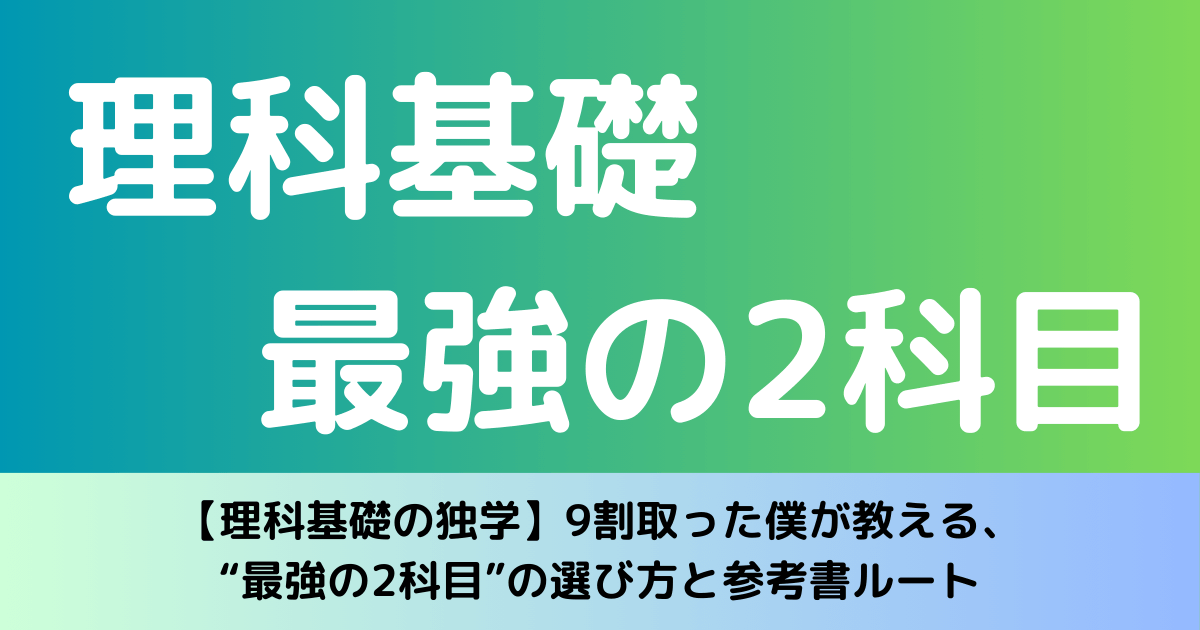【理科基礎の独学】9割取った僕が教える、“最強の2科目”の選び方と参考書ルート
こんにちは!独学受験ラボの芹谷です。
「理科基礎って、どの科目を選べばいいの?」
「正直、主要科目が忙しくて、対策が後回しになっちゃってる…」
多くの文系受験生が、共通テストでしか使わない「理科基礎」の扱いに、頭を悩ませています。
しかし、断言します。理科基礎は、正しい戦略で挑めば、あなたの合否を左右する「戦略的得点源」に変わります。
この記事では、僕が実際に学校指定の科目を捨て、独学で選んだ2科目で93点を取った経験から、
- 高得点を狙うための「最強の2科目」の選び方
- 11月からでも間に合う、たった2冊で完成する参考書ルート
について、僕のリアルな体験談を交えて、徹底的に解説していきます。
【最重要】「学校の授業」を信じるか、「自分の戦略」を信じるか
まず、大前提となるあなたの状況を診断します。
パターンA:「授業をある程度理解している」なら、学校の科目でOK
もし、あなたが学校の理科基礎の授業を聞いていて、内容がある程度理解できているのであれば、無理に科目を変更する必要はありません。
学校の授業と、この後紹介する参考書を組み合わせるのが、最も効率的なルートです。
パターンB:僕のように「授業を内職に充てている」なら、学校は無視してOK
一方で、僕のように、学校の授業が自分のレベルに合わず、その時間を他の科目の勉強(内職)に充てているのであれば、話は別です。
君は、学校で指定されている科目に関係なく、ゼロから、最も合格可能性の高い科目を独学するべきです。
【僕の体験談】学校指定の「化学基礎」を捨て、独学で「地学基礎」を選んで大正解だった話
僕の学校も、「生物基礎」と「化学基礎」が指定科目でした。
しかし、僕は「化学基礎」が自分に向いていないと判断し、独学で「地学基礎」を学習して受験に臨みました。
結果は93点。周りが学校の授業に縛られる中、「自分の頭で戦略を立てる」というこの決断が重要でした。
【科目選択編】9割を目指すなら「生物基礎」と「地学基礎」一択。その明確な理由
では、パターンBの君は、どの科目を選ぶべきか。結論から言います。
結論:「生物基礎」と「地学基礎」が、最も暗記量が少なく、高得点を狙いやすい
理科基礎4科目の中で、この2科目は計算問題が非常に少なく、ほとんどが知識の暗記と思考力で対応できます。そのため、短期間でのキャッチアップが最も容易なのです。
なぜ「化学基礎」は避けるべきなのか?(計算・暗記量のコスパが悪い)
化学基礎は、計算問題と暗記の両方がバランス良く出題されるため、一見すると対策しやすそうに見えます。しかし、裏を返せば、どちらも中途半端になりがちで、高得点を安定させるのが難しい科目です。
「物理基礎」は、数学が得意な受験生だけの“ロマン”
物理基礎は、暗記量が最も少ない科目です。
しかし、その分、数学的な思考力と計算力が高度に要求されます。数学が得意で、時間をかけられるなら良いですが、そうでないなら避けるのが賢明です。
【地理選択者へ】地理と、生物基礎・地学基礎の、最高のシナジーを解説
もし君が地理選択者なら、この組み合わせは最強です。
地学基礎で学ぶプレートテクトニクスは、地理の地形分野に直結しますし、生物基礎のバイオーム(植生)の知識は、地理の気候分野でそのまま使えます。
この相乗効果は、計り知れないアドバンテージになります。
【参考書ルート編】僕が9割取るために使ったのは、たった2冊+過去問だけ
僕がこの2科目に使った参考書は、インプット用とアウトプット用の、それぞれ1冊ずつだけです。
STEP1(インプット):『きめる!共通テスト』で、基礎を完璧に理解する(11月〜)
【僕のタイムライン】
僕が理科基礎の本格的な対策を始めたのは、11月からでした。それくらい、短期間で仕上げることが可能なのです。
インプットに使ったのは、『きめる!共通テスト』シリーズです。
なぜ、有名な『はじめからていねいに』ではなく『きめる!』なのか?
『きめる!』は、共通テストでよく出題される内容が明確化されているため、学習効率が高いのです。
また、完全に好みですが、僕にとっては『きめる!』の方が、図や解説がシンプルで、圧倒的に読みやすく、分かりやすかったからです。
この参考書を、まずは1〜2周通読し、重要語句を覚え、図やグラフの内容を自分の言葉で説明できるようになるまで、完璧に仕上げます。
僕はこのインプット作業を、11月末までに終わらせました。
STEP2(知識の補足+演習):『集中講義』で、アウトプットに慣れる(12月上旬〜)
【僕のタイムライン】
12月に入ってから、僕は『共通テスト 集中講義』シリーズで、アウトプットの練習を始めました。
『きめる!』で学んだ知識を、よりコンパクトな『集中講義』で再確認し、付属の問題でアウトプットの練習を始めます。
ここで初めて、「知識はあるのに、問題形式になると解けない」という自分の弱点に気づくはずです。
その弱点を、『きめる!』に戻って潰していく。このサイクルを、12月上旬で終わらせました。
STEP3(最終仕上げ):『共通テスト過去問』で、時間配分と形式をマスターする(12月中旬〜)
2冊を終えたら、あとはひたすら共通テストの過去問を解き、時間配分と、共通テスト特有の問題形式に慣れるだけです。
まとめ:理科基礎は「賢く」戦えば、必ず君の武器になる
理科基礎は、多くの文系受験生が、その重要性に気づいていながらも、対策を後回しにしがちな科目です。
しかし、この記事で紹介したように、正しい「科目選択」と効率的な「参考書ルート」で「賢く」戦えば、たった2ヶ月程度の学習でも、9割以上を狙える、非常にコストパフォーマンスの高い科目なのです。
理科基礎で安定して高得点を取ることができれば、それは主要科目の負担を減らし、君の精神を安定させてくれる、強力な「武器」になります。
ぜひ、この戦略を参考に、理科基礎を得点源に変えてください。
応援しています!