【地理論述の書き方】『納得できる地理論述』とスタディサプリを併用した僕の独学勉強法
こんにちは!独学受験ラボの芹谷です。
「知識はあるはずなのに、何を書けばいいか分からない…」
「答案用紙を前に、ただ時間だけが過ぎていく…」
国公立大学の二次試験や、一部の私立大学で課される「地理論述」。 多くの独学受験生が、この「書く力」の対策に悩み、十分な得点を取れずに涙をのんでいます。
僕も、そうでした。 「知識はあるのに、どう文章にすれば点数になるんだ…」と、迷っていました。
しかし、僕はそこから、ある「最強の組み合わせ」によって、論述への苦手意識を克服し、得点源に変えることができました。
この記事では、僕が実践した、参考書『納得できる地理論述』とスタディサプリを連携させた、独学者のための地理論述・完全攻略法について、その全手順を徹底解説します。
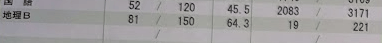
▼ この参考書ルートの位置付け
前の記事: 『統計・データが面白いほどわかる本』で、データを完全攻略
この記事: 国公立二次向け 『納得できる地理論述』×『スタサプ』で、論述演習
>> 地理の全参考書ルート(全体図)はこちら
なぜ、独学の「地理論述」対策は、ほとんどの受験生が挫折するのか?
多くの受験生が陥る「何を書けばいいか分からない」という壁
論述問題で点が取れない原因は、知識不足だけではありません。
むしろ、「設問の要求を読み取り、どの知識を、どういう順番で、何文字でまとめるか」という「答案の作り方」を知らないことが、最大の原因です。
【大前提】この特訓を始める前に、必ず終えておくべきこと
論述は、盤石な基礎知識があって初めて書けるものです。
もし、まだ地理の全体像や共通テストレベルの知識に不安がある場合は、必ず以下の記事で紹介している参考書から先に取り組んでください。
順番を間違えると、学習効果が半減してしまいます。
【前提記事】地理の土台は万全ですか?
→ STEP1&2: 『きめる!』と『地理集中講義』で基礎を固める
この壁を越える鍵は「型」のインプットと「思考法」の理解にある
そして、この「答案の作り方」は、センスや才能ではありません。
明確な「型」と「思考法」が存在する、再現性の高い技術です。
独学でも、正しいツールを使えば、誰でも身につけることができます。そのためのツールが、『納得できる地理論述』とスタディサプリでした。
最強のタッグ!『納得できる地理論述』と「スタサプ」それぞれの役割
この2つの教材を、僕はそれぞれ明確な役割分担で使っていました。
役割①【教科書・問題集】:論述の「型」を学ぶための『納得できる地理論述』
この参考書が果たす役割は、論述答案という「完成品」の、完璧な「設計図」をあなたに提供することです。
本書では、地理論述で問われる問題がいくつかの「型」に分類されています。
そして、それぞれの「型」ごとに、「設問の要求は何か→使うべき知識は何か→どういう順番で書くか」という思考の流れが、フローチャート形式で、非常に分かりやすく解説されています。
つまり、この一冊で、あなたはどんな問題にも対応できる、論理的な答案構成の「引き出し」を手に入れることができるのです。
役割②【専属講師】:答案の「作り方」を学ぶためのスタディサプリ地理論述講座
そして、独学受験生にとって、この上なくありがたいのがスタディサプリの鈴木達人先生による『地理論述講座』です。
例えるならば、あなただけの「専属講師」です。
参考書だけでは分かりにくい、「問題を前にして、達人先生が“リアルタイム”で何を考え、どう答案を組み立てていくか」という、思考のプロセスそのものを、ライブ感たっぷりに見せてくれます。
【僕が実践】この2つを連携させ、論述力を爆上げする3ステップ勉強法
僕はこの2つの教材を、以下のサイクルで連携させることで、論述への苦手意識を完全に克服しました。
STEP1:まず、スタディサプリの講義で、鈴木達人先生の「思考プロセス」を盗む
最初に、その日に学ぶテーマについて、スタディサプリの地理論述講座を視聴します。
ここで重要なのは、鈴木先生が、問題をどう読み解き、どの知識を使い、どう答案を組み立てているのか、その「思考のプロセス」を完全に理解することです。
参考書を読むだけでは決して学べない、プロの「頭の中」を覗き見る感覚で、授業に集中してください。
STEP2:次に『納得できる地理論述』で、同じようなテーマの問題を、自力で解いてみる
スタディサプリで学んだ「思考法」を元に、今度は『納得できる地理論述』の同じようなテーマの問題に、自力で挑戦します。
これが、インプットした知識を、実際に「書ける」力に変えるための、最も重要なアウトプットの訓練になります。
STEP3:最後に、参考書の解説と模範解答を熟読し、自分の答案と比較・分析する
自分の答案と、参考書の模範解答を徹底的に比較します。
「どの要素が足りなかったのか」「なぜ、このキーワードが必要だったのか」を分析し、自分の答案を、自分で添削するのです。
この作業を繰り返すことで、あなたの答案の質は飛躍的に向上します。
【今の時代の最強の武器】AIによるセルフ添削
ここで、現代の独学受験生である君にしか使えない、最強の武器を紹介します。
それは、AIを活用した「セルフ添削」です。
やり方は簡単です。自分の書いた答案と、参考書の模範解答をそれぞれ用意し、AIにこう指示してみてください。
「あなたは地理の専門家です。以下の私の答案と模範解答を比較し、良い点、足りない点、そして改善点を具体的にフィードバックしてください」
これにより、独学では得られなかった「客観的な第三者の視点」を、いつでも、何度でも手に入れることができます。
これは、高価な予備校の添削サービスに匹敵する、革命的な武器です。ぜひ活用してください。
なぜこの「参考書×映像授業」の併用が、独学者にとって最強なのか?
メリット①:論述の「静的な型」と「動的な思考」を同時に学べる
『納得できる地理論述』で答案の完成形である「静的な型」を学び、スタディサプリでその答案を作り上げるまでの「動的な思考」を学ぶ。
この両輪を回すことで、論述力は最短で向上します。
メリット②:独学者が最も困る「添削なし」の状態を、限りなくカバーできる
鈴木先生の解説や、AIによるセルフ添削は、第三者による「模範的な添削」の役割を果たしてくれます。
これにより、「自分の答案の、どこがどうダメなのか分からない」という独学最大の悩みを、限りなくゼロに近づけることができます。
僕の体験談:好きな地理の勉強として、夜にじっくり取り組むのが最高の時間だった
僕は、スキマ時間に『統計データの本』を進め、この論述対策は、一番集中できる夜の時間に、じっくりと取り組むようにしていました。地理が好きだった僕にとって、この「思考力を鍛える」時間は、受験勉強の中でも特に楽しいひとときでした。
この特訓を終えた後、あなたの「書く力」はどう変わるか
卒業の目安:どんな問題を見ても、最初に「答案の設計図」が頭に浮かぶ
論述問題を前にした時、「何を書こう…」と手が止まるのではなく、「この問題の要求は〇〇だから、AとBの要素を、この構成で書けばいいな」と、答案の「設計図」が瞬時に頭に浮かぶようになれば、卒業の合図です。
次のステップは、いよいよ志望校の「過去問」での実践演習
この2つの教材で「型」と「思考法」をマスターしたら、あとは志望校の過去問を使い、ひたすら実践演習を積むだけです。
【あわせて読みたい】
▼論述と並ぶ、もう一つの武器「データ問題」を攻略する
論述と並んで、地理の合否を分けるのが「統計・データ問題」です。僕がスキマ時間を活用して、この分野を得意に変えた勉強法も、別の記事で詳しく解説しています。
→『地理B 統計・データの読み方が面白いほどわかる本』の詳しい使い方
まとめ:「書けない」不安を「書ける」自信に変え、論述を得点源にしよう
地理論述は、多くの受験生が苦手とする、そして対策を後回しにしがちな分野です。
しかし、それは逆に言えば、正しく対策すれば、ライバルに圧倒的な差をつけることができる「ブルーオーシャン」だということ。
この記事で紹介した「参考書」と「スタディサプリ」という最強のタッグ、そして「AI添削」という現代の武器を使いこなし、ぜひ、「書けない」不安を、「書ける」自信に変えてください。
論述を得点源にできた時、あなたの志望校合格は、もう目の前です。 応援しています!
【地理学習の全体像はこちら】
▼高3夏から僕が偏差値を20上げた、地理の参考書ルートの全て
今回紹介した「論述対策」は、僕の地理学習ルートの最終仕上げとなる重要なステップでした。僕がどのようにして地理の偏差値を20上げたのか、その参考書ルートの全体像は、こちらの記事で全て公開しています。
→【独学で地理は間に合う!】僕が実践した「地理」の最短・最速攻略ルートを読む








