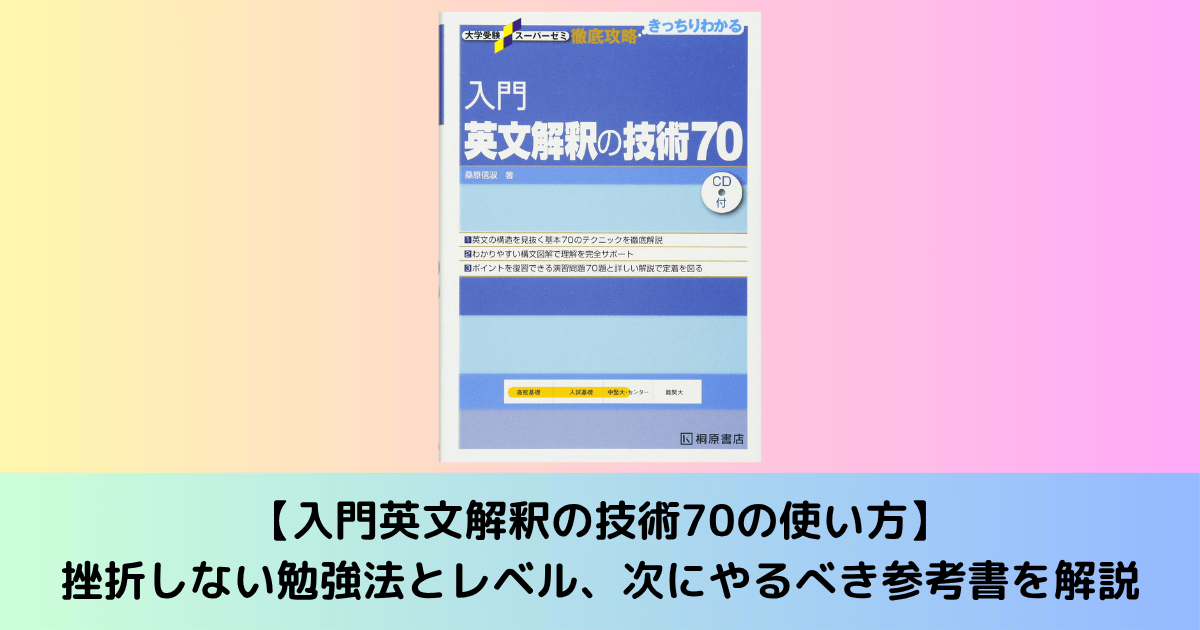【入門英文解釈の技術70の使い方】挫折しない勉強法とレベル、次にやるべき参考書を解説
こんにちは!独学受験ラボです。
「英文法は一通りやったはずなのに、一文が長くなると、途端に構造が分からなくなる…」 「SVOCを振るのが苦手で、なんとなくフィーリングで読んでしまっている…」
基礎的な英文法を学んだ全ての受験生が、次にぶつかる大きな壁。それが「英文解釈」です。
この「わかる」と「できる」の間にある深い溝を埋め、英文法の知識を、長文を読み解くための「実践的な武器」に変えてくれるのが、今回紹介する『入門英文解釈の技術70』です。
この記事では、僕がこの参考書をどのように使いこなし、複雑な英文を正確に読み解く力を身につけたのか。
その具体的な勉強法と、僕自身の体験、そして現在の視点から見た最適な参考書ルートまで、余すところなくお話しします。
▼ この参考書ルートの位置付け
前の記事: 『肘井の読解のための英文法』で、解釈の「理屈」を学ぶ
この記事: 『入門英文解釈の技術70』で、解釈を「実践」し定着させる(←今ココ)
次の記事: 『パラグラフリーディングのストラテジー』で、論理的な読み方をマスターする
>> 英語の全参考書ルート(全体図)はこちら
『入門 英文解釈の技術70』はどんな参考書?その役割とレベルを解説
役割:「読める」を「正確に訳せる」に変える、解釈の本格的な一冊目
『肘井学の読解のための英文法【必修編】』が文法と解釈の「橋渡し」だとしたら、本書は橋を渡った先にある「最初の関所」です。ここを乗り越えることで、あなたの読解精度は飛躍的に向上します。
対象レベル:日東駒専〜MARCHレベルの壁を越えたい受験生
この参考書がターゲットとするのは、日東駒専レベルの英文は読めるけれど、MARCHレベルになると手こずる、というレベルの受験生です。ここをマスターすることが、MARCH合格への大きな一歩となります。
始める前の必須条件:『肘井学の読解のための英文法【必修編】』レベルの知識は必要
ただし、この本で挫折しないために、前提として基礎的な英文法の知識と、一文の構造をある程度見抜ける力が必要です。具体的には、『肘井学の読解のための英文法【必修編】』を終えていることが、この本に取り組むための最低条件だと考えてください。
【あわせて読みたい】
▼前提となる一冊『肘井の読解のための英文法【必修編】』の詳しい使い方はこちら
「そもそも『肘井の読解のための英文法【必修編】』ってどんな参考書?」「どう使えばいいの?」と疑問に思った方は、まずはこちらの記事から読んでみてください。僕が実践した「3周勉強法」を徹底解説しています。
【正直に話します】僕が『技術70』を選んだ理由と、今、本当におすすめしたい一冊
ここが、他のどのサイトにも書かれていない、僕自身の本音です。
僕が受験生時代に『技術70』を使った、たった一つの理由
僕がこの参考書を選んだ理由は非常にシンプルで、「当時はこの参考書が、英文解釈の王道ルートとして最も有名だったから」です。情報が少ない独学受験生にとって、多くの先輩が使っているという事実は、何よりの安心材料でした。
【もし今、僕が受験生なら】『大学入試 英文熟考 上』を選ぶかもしれない理由
ただ、正直に言うと、もし僕が今の受験生なら、『大学入試 英文熟考 上』という、もう一つの選択肢を真剣に検討します。
なぜなら、『英文熟考』は解説が『技術70』よりもさらに詳しく、英文の本質的な理解を促す工夫が随所に凝らされているからです。解説音声が付いているのも、独学者には非常に大きなメリットです。
もし選ぶなら、『肘井学の読解のための英文法【必修編】』の次に『英文熟考 上』に進み、それが完璧になったら『英文熟考 下』に進むのが良いでしょう。ただし、『下』はかなり難しいので、注意してください。
結論:どちらを選んでもOK。大切なのは「使い方」です
もちろん『技術70』も、今なお多くの受験生に愛される素晴らしい参考書です。どちらを選んでも、正しい使い方でやり込めば、必ず力はつきます。重要なのは「どちらを選ぶか」よりも「どう使うか」。これから、僕が実践した具体的な勉強法を解説します。
この一冊を完璧にする、僕がおすすめする4ステップ勉強法
STEP1:まずはノーヒントで、「構文」を自力で把握する
この参考書は使われている単語が少し難しいので、いきなり完璧な和訳を書き出そうとするのは不要です。挫折の原因になります。
最初のステップは、和訳はできなくても良いので、まずは自力でSVOCを振り、文の構造がどうなっているかを把握することに全集中してください。
STEP2:解説と構文図解を熟読し、自分の「解釈のズレ」を分析する
自力で構文を考えたら、すぐに解説を読みます。
SVOCの振り方、修飾関係の把握など、自分の解釈がどこで、なぜ間違っていたのか、その原因を徹底的に分析します。
STEP3:もう一度、今度は「意味の通る和訳」を組み立てる
解説を理解した上で、もう一度英文と向き合います。ここでも、模範解答のような綺麗な日本語訳を作る必要はありません。 この参考書の和訳は、正直なところ綺麗すぎます。
大切なのは、SVOCの構造通りに、意味の通る日本語として頭の中で組み立てられるかどうかです。模範解答と意味の方向性が合っていればOK。細かい表現にこだわりすぎないようにしましょう。
STEP4:付属CDを使い、最低10回は音読して体に染み込ませる
最後に、完全に理解した英文を、付属のCDやダウンロード音声を使いながら、体に染み込ませます。目安として10回音読を推奨します。
【重要】付属CD(音声)の戦略的活用法で、学習効果を最大化する
目的①:「返り読み」を矯正し、速読力を鍛える
音読は、英語をいちいち日本語に訳さず、英語の語順のまま理解する「英語脳」を作るための最高のトレーニングです。これが、速読力に直結します。
目的②:リスニングの基礎体力をつける
ネイティブの正しい発音とリズムを繰り返し聞くことで、自然とリスニングの基礎体力も向上します。
『入門英文解釈の技術70』が終わったら?次に繋げる参考書
卒業の目安:掲載されている英文の構造を、他人に説明できるレベル
本書の発展問題を含め、掲載されている英文の構造を、なぜそうなるのか、他人に理路整然と説明できるようになったら、卒業の合図です。
次のステップは「長文の読み方」の習得へ。『パラグラフリーディングのストラテジー』
多くの参考書ルートでは、ここでさらに難しい長文問題集に進みます。しかし、僕が強く推奨するのは、その前に一度「長文全体の論理的な読み方」を学ぶことです。
僕がここで取り入れたのが、『パラグラフリーディングのストラテジー』です。難しい英文ほど、闇雲に読むのではなく、ディスコースマーカー(接続詞など)に注目して、効率よくかつ論理的に読むことが効果的だからです。
【あわせて読みたい】
▼【次のステップ】「一文」から「文章全体」へ。論理的な読み方を学ぶ
『技術70』で一文を「ミクロ」に、正確に読む力を手に入れたあなたへ。次なる壁は、長文全体の論理構造を「マクロ」に捉えることです。
僕が「フィーリング読み」を卒業し、正答率を劇的に安定させた「パラグラフリーディング」の具体的な勉強法を、以下の記事で徹底解説しています。
その後、本格的な長文演習(『ポラリス2』など)に進む
「読み方の型」を学んだ後で、『英語長文ポラリス2』や『The Rules3』といった、本格的な長文演習に進む。この順番こそが、挫折しないための王道ルートです。
まとめ:『技術70』で、どんな複雑な英文も怖くないという自信を手に入れよう
『入門英文解釈の技術70』は、あなたがこれまで学んできた英文法の知識を、ただの暗記項目から、長文を読み解くための「実践的な武器」へと変えてくれる、素晴らしい一冊です。
この本で正しい「読み方」の型を身につければ、この先の長文演習の世界が、驚くほどクリアに見えるようになるはずです。
ぜひ、この「関所」を突破して、難関大の長文にも臆することなく立ち向かえる、本物の「解釈力」と「自信」を手に入れてください。 応援しています!
【英語学習の全体像はこちら】
▼偏差値50から70まで駆け上がった、僕の英語勉強法の全て
今回紹介した『入門英文解釈の技術70』は、僕の独学ルートの中でも、読解の精度を飛躍的に高めてくれた重要な一冊でした。
単語、文法、そしてこの後の長文演習まで、僕が偏差値50から70まで駆け上がった英語の勉強法の全体像は、こちらの記事で全て公開しています。