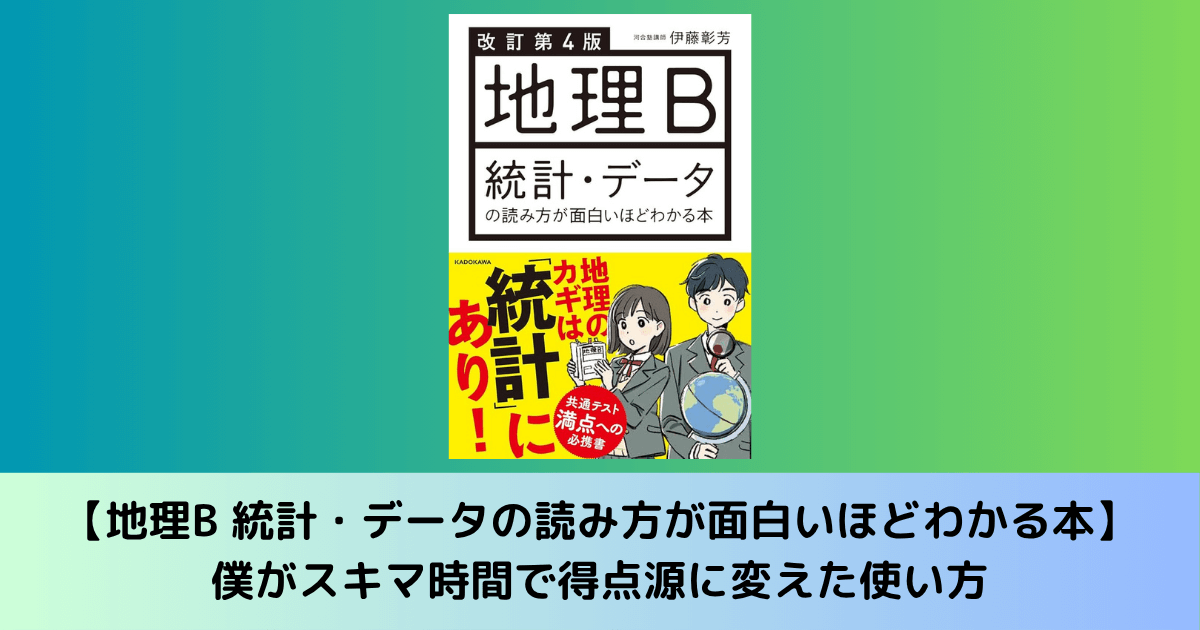【地理B 統計・データの読み方が面白いほどわかる本】僕がスキマ時間で得点源に変えた使い方
こんにちは!独学受験ラボの芹谷です。
「この統計グラフ、どの国がどの線なのか、さっぱり分からない…」 「貿易相手国の順位なんて、全部暗記するしかないの…?」
共通テストの地理で、多くの受験生が頭を抱えるのが、「統計・データ問題」です。
僕も、この分野が本当に苦手でした。
この記事では、そんな僕が、ある一冊の参考書を使い込み、地理の合否を分けるこの分野を、確固たる「得点源」に変えることができた、その具体的な使い方と勉強法について徹底解説します。
その参考書が、『地理B 統計・データの読み方が面白いほどわかる本』です。
▼ この参考書ルートの位置付け
前の記事: 『共通テスト集中講義 地理』で、知識の補完と演習準備
この記事: 『統計・データが面白いほどわかる本』で、データを完全攻略
次の記事: 国公立二次向け 『納得できる地理論述』×『スタサプ』で、論述演習
>> 地理の全参考書ルート(全体図)はこちら
なぜ、地理の合否は「統計・データ問題」で決まるのか?
僕もハマった「国の絞り込みができない」というワナ
この参考書に取り組む前の僕は、模試で統計問題が出てくるたびに、頭を抱えていました。
細かいデータの傾向が頭に入っていなかったので、例えば3つの国の産業別の人口比率グラフを見せられても、「どの国がどれだ?」と、1つに絞り込むことができなかったのです。
この「なんとなく」で解いて失点するパターンこそ、多くの受験生が地理で高得点を取れない最大の原因です。
「知識」だけでなく、データの「読み方」を知る者が勝つ
統計・データ問題は、単なる暗記ではありません。
与えられたグラフや表から、「どこに注目し」「どの知識と結びつけ」「どう考えれば答えが導き出せるか」という、データの「読み方」を知っている者が、圧倒的に有利になる世界です。
この本は、まさにその「読み方」を教えてくれます。
『統計・データの読み方が面白いほどわかる本』はどんな参考書?
役割:地理のデータ問題を「得点源」に変える、最強の特化型参考書
この本の役割は非常に明確です。それは、地理のあらゆる統計・データ問題の「目のつけどころ」と「思考法」を学ぶこと。
地理学習の仕上げとして、この一冊を完璧にすれば、あなたの得点は飛躍的に安定します。
対象レベル:『地理集中講義』までを終え、さらなる上乗せを狙う全受験生
この本は、『村瀬のゼロからわかる地理B』や『共通テスト 地理 集中講義』などで、地理の基礎知識を一通りインプットし終えた受験生が、さらなる得点力アップを目指すために使う、仕上げの一冊です。
【前提記事】この本に取り組む前に
この参考書は、地理の基礎知識が固まっていることが大前提です。 もし、まだインプットや基本的な演習に不安がある場合は、必ず以下の記事で紹介している参考書から始めてください。順番を間違えると、学習効果が半減してしまいます。
→ STEP2: 『地理集中講義』で「わかる」を「解ける」に変える
【最重要】この参考書を使い始める前に、絶対に知っておくべきこと
本書は非常に優れた参考書ですが、出版から年数が経っているため、一部の統計データが古くなっている可能性があります。
そのため、必ず『データブック オブ・ザ・ワールド』のような最新の統計資料集を隣に置き、データを確認・更新しながら進めることが、この本を使いこなす上での絶対条件です。
【僕が実践】スキマ時間をフル活用する、効率的な使い方
僕の基本戦略:通学中の電車が「データ分析の特別講義」に変わる
僕は、この参考書に、まとまった勉強時間を使いませんでした。
その代わり、通学中の電車の中などの「スキマ時間」に、毎日少しずつ進めることを徹底していました。 この本はハンディサイズで持ち運びやすく、1テーマが見開きで完結するため、スキマ時間学習との相性が抜群です。
重い参考書を持ち歩かなくて良いので、心理的なハードルが低いのも、継続できた大きな理由でした。
STEP1:「基本データ」のページを読み、各統計の「傾向」を頭に入れる
まずは各テーマの基本データをインプットします。
「米の生産量トップ3は、中国、インド、バングラデシュ…」といった基本的な知識と、その背景にある「なぜ、そうなるのか」という理由を、セットで頭に入れていきます。
STEP2:「例題」を解き、データの「どこに注目すべきか」を学ぶ
次に、例題を解きます。しかし、ここで重要なのは正解することではありません。
本書の神髄である「目のつけどころ」の解説を熟読し、「なるほど、このグラフでは、まず一人あたりGNIと総人口の関係に注目すればいいのか」という、専門家の「視点」をインストールすることが最大の目的です。
STEP3:間違えた問題は、その場でスマホや資料集で徹底的に調べる
スキマ時間学習だからこそ、分からない点を放置しないことが重要です。
間違えた問題や、納得いかない解説があれば、その場でスマホや資料集で徹底的に調べ、知識の穴を完全になくしていきました。
この一冊で、僕の「地理的思考力」はどう進化したか
体験談:単なる数字の羅列が、意味のある「物語」として見えてくる
この参考書で勉強を続けるうちに、僕の中で大きな変化が起きました。
これまで単なる数字の羅列にしか見えなかった統計データが、次第に、「国の個性を示すプロフィール」のように見えてきたのです。
「この国は高齢化が進んでいるから、労働力不足を補うために、こういう産業が強いんだな」といったように、数字の裏にある背景や物語が読み解けるようになっていきました。
結果:共通テストだけでなく、国公立二次の論述問題にも活きる力がついた
データ問題の克服は、思わぬ副産物ももたらしてくれました。
それは、国公立の二次試験で求められる「論述力」の向上です。
統計データの背景を考察する訓練を積んだことで、論述問題で具体例を挙げる際の引き出しが圧倒的に増え、答案の質が格段に上がったのです。
まとめ:データ問題を「武器」に変え、ライバルに圧勝しよう
『地理B 統計・データの読み方が面白いほどわかる本』は、多くの受験生が苦手とする分野を、あなたの「最強の武器」に変えてくれる可能性を秘めた一冊です。
この本でデータ問題への苦手意識をなくし、「むしろ、データ問題よ、かかってこい!」と思えるようになれば、あなたの合格は、もう目の前です。 応援しています!
【地理学習の全体像はこちら】
▼高3夏から僕が偏差値を20上げた、地理の参考書ルートの全て
今回紹介した『統計・データ本』は、僕の地理学習ルートの「最後の仕上げ」となる一冊でした。僕がどのようにして地理の偏差値を20上げたのか、その参考書ルートの全体像は、こちらの記事で全て公開しています。